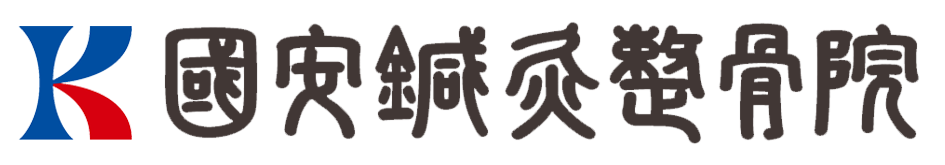【鍼灸EBM最前線:鍼のエビデンスの現状「鍼がポジティブな効果を出す可能性が高い疾患」(10)「尿失禁】
2025年2月26日「鍼におけるエビデンスの現状:2017年から2022年の鍼のシステマティックレビューとメタアナリシスのレビュー」
82疾患が「鍼がポジティブな効果を出す可能性が高い疾患(Evidence of potential positive effect)」です。
以下、引用。
【泌尿器疾患】
Urological diseases
「尿失禁(Urinary incontinence)」
Urinary incontinence
以上、引用終わり。
「尿失禁」について、日本では2004年に『EBMに基づく尿失禁診療ガイドライン』が出版されています。
2013年に『女性下部尿路症状診療ガイドライン』が日本排尿機能学会から出版され、
2019年に『女性下部尿路症状診療ガイドライン(第2版)』が出版されており、鍼に関する記述もありますが、推奨グレードはC1で「女性下部尿路症状に対する有効性は十分証明されていない(レベル3)」になります。
また、「過活動膀胱」の概念は1997年に生まれました。鍼灸学校で習った記憶が無かったのですが、新しい概念です。
↓
2011年
「過活動膀胱の症状に基づく診断:概要」
※「「過活動膀胱」という用語は、1997 年にポール・エイブラムス博士とアラン・ウェイン博士によって、下部尿路症状とその治療について議論するために開催されたシンポジウムのタイトルとして造られました。」
※「後に 1999 年に正式化された過活動膀胱(OAB)の定義は、「下部尿路機能障害を示唆する症状症候群」であり、具体的には「基礎にある代謝性または病的状態がなく、切迫性尿失禁の有無にかかわらず、通常頻尿と夜間頻尿を伴う尿意切迫感」と定義されました。2002年に国際失禁学会(ICS)がこの定義を正式に採用しました」
「尿失禁」の分類は、「腹圧性尿失禁」…クシャミや笑ったら尿が漏れる。
「切迫性尿失禁」…突然、尿意を感じたら尿が漏れる。
「混合性尿失禁」…腹圧性尿失禁と切迫性尿失禁の両方の特徴がある。
「溢流性尿失禁(いつりゅうせいにょうしっきん)」…自分で尿を出したいのに出せない、でも尿が少しずつ漏れ出てしまう。
「機能性尿失禁」の5分類があります。
2013年のコクランシステマティックレビューは以下のように結論しています。
↓
2013年7月1日『コクランシステマティックレビュー』
「成人の緊張性尿失禁に対する鍼療法」
※「【著者の結論】緊張性尿失禁の成人における鍼療法の効果は明らかではない。鍼療法が薬剤治療よりも効果的であると決定するエビデンスは十分ではない。
2017年の『アメリカ医師会雑誌(JAMA)』のランダム化比較試験は腰仙部の電気鍼が尿失禁を少なくしたとしています。
↓
2017年6月27日『アメリカ医師会雑誌(JAMA)』
「腹圧性尿失禁女性の尿漏れへの電気鍼の効果:ランダム化比較試験」
以下、引用。
「【結論】腹圧性尿失禁の女性の腰仙骨部への電気鍼は、偽電気鍼と比較して、6週間にわたって、より尿失禁が少なくなった。」
以上、引用終わり。
2020年のシステマティックレビューは、ストレス性尿失禁に対する電気鍼に対して、肯定的です。
↓
2020年10月12日『国際医学研究ジャーナル』
「電気鍼療法は女性の腹圧性尿失禁の治療に安全で効果的ですか?システマティックレビューとメタ分析」
※「それにもかかわらず、現在のエビデンスの状況は、腹圧性尿失禁SUIに対する鍼治療の有効性については議論の余地があることを意味します。たとえば、手技鍼MA、電気鍼EA、その他の鍼治療法を含む標準的な介入を調査した2013年のメタアナリシスでは、鍼治療が腹圧性尿失禁SUIに不確実な治療効果をもたらしたことが示されました。」
「異なる周波数の電気鍼(2Hzおよび100Hz)を使用すると、排尿筋機能を正常またはほぼ正常に調整できます。」
2022年の香港理工大学のシステマティックレビューは、より肯定的です。
↓
2022年7月17日香港理工大学
『エクスプロア』
「女性の尿失禁の治療のための様々な形態の鍼灸の有効性:システマティックレビューとメタアナリシス」
以下、引用。
「【結論】このレビューに基づけば、電気鍼は、女性のストレス性尿失禁(SUI)を改善するかもしれない」
以上、引用終わり。
2023年
「1992年から2022年までの腹圧性尿失禁に対する鍼治療の研究動向:ビブリオメトリック計量書誌学分析」
※「日本の東京医科歯科大学は、1992年に最初の切迫性尿失禁(SUI)論文を発表しましたが、中国は2008年まで論文を発表していません」
↑
尿失禁の鍼の論文について、1990年代までは、日本は鍼の論文で世界をリードしており、2008年まで中国は発表していません!!!しかし、その後で、中国は論文数で世界一となります。1950年代から1970年代までは、鍼の学術レベルは日本が世界の中心でした。1970年代に鍼麻酔ブームが起こり、1980年に全日本鍼灸学会が組織され、1987年に世界鍼灸学会連合会(WFAS)がつくられます。2002年に中国が世界貿易機関(WTO)に加盟して、急激な経済成長が起こり、2010年に中国はGDPで日本を追い抜いて世界第2位の経済大国となります。2008年に中国は最初の尿失禁の鍼研究の論文を発表し、そこから日中は逆転していきます。わたしの実感でも2000年代から日本の学術は停滞し、「失われた20年」という個人的な印象となります。
2024年5月に世界鍼灸学会連合会(WFAS)は、尿失禁の鍼灸ガイドラインを発表しています。これは趙吉平先生が著者であり、非常に高品質だと感じました。
↓
2024年5月
「鍼灸診療ガイドライン:女性の尿失禁」
以下、引用。
「【DPSLAT:腰仙部のツボへの鍼の深刺刺激療法】」
「腰仙部のツボである上髎(BL31)、次髎(BL32)、中髎(BL33)、下髎(BL34)、会陽(BL35)、秩辺(BL54)を50mm以上の深さで穿刺し、会陰部の強い放射感覚を主な刺鍼感覚として得る鍼療法、および刺鍼感覚を高める電気鍼療法。」
以上、引用終わり。
プロフェッショナルの鍼灸師として知っておくべきなのは、三陰交(SP6)穴への『経皮性脛骨神経刺激』という鍼をもとにした新しい西洋医学の治療法です。
2019年の日本泌尿器科学会『女性下部尿路症状診療ガイドライン [第2版]』にも経皮性脛骨神経刺激(PTNS)について200ページに記述があります。
↓
以下、引用。
「【推奨グレード】保留:保険適用外】
欧米では、過活動膀胱に対し、大規模RCTによる有効性を支持する根拠がある(レベル1)が、本邦では保険適応はない」
「S3領域の末梢神経すなわち後脛骨神経(踝の3~5cm頭側の三陰交というツボ)に鍼を挿入または表面電極を装着し、電気刺激する方法である」
以上、『女性下部尿路症状診療ガイドライン [第2版]』より、引用終わり。
三陰交(SP6)で脛骨神経を刺激することは、西洋医学の世界では、カルフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)医学部のマーシャル・ストーラー(Marshall L Stoller)教授によって、1999年に学会のポスター発表で報告されました。当時は三陰交に針を刺しての電気刺激です。最初の名前は「ストーラー求心性神経刺激(SANS)」というデバイスを使い、2000年にはFDAに認可されました。
2005年頃にマーシャル・ストーラー教授は、TENSのような経皮性の刺激「経皮性脛骨神経刺激(PTNS)」を開発しました。
2012年にはEBМのコクランレビューで過活動膀胱への選択肢として推奨されました。
↓
2012年コクラン・システマティックレビュー
「成人の非神経因性過活動膀胱に対する抗コリン薬と非薬物活性療法の比較」
ここで、気になるのは、メカニズムです。
論文を読むと「脛骨神経(Tibial nerve)」はL4~S3であり、
「排尿筋(detrusor)」や「骨盤底筋」はS3の支配であり、
S3神経を通じて骨盤底筋や排尿筋に働きかけるとストーラー教授は述べています。
また、西洋医学では、「仙骨神経刺激療法(SNM:Sacral Neuromodulation:セイクラル・ニューロモデュレーション)」という仙骨神経のS3・S4の近くに電気デバイスを植えこむ電気刺激療法があります。
1981 年に Tanagho と Schmidt は、仙骨神経根 S3 を持続的に刺激すると、排尿筋と括約筋の活動が調整されることを観察しました。
1990年代に最初の埋め込み型仙骨神経刺激デバイスが開発され、1997年にアメリカFDAによって切迫性尿失禁のデバイスとして承認されました。
2017年から過活動膀胱に対して日本でも保険適応されています。
↓
2024年スタットパールス
「仙骨神経刺激法(セイクラル・ニューロモデュレーション)」
※「仙骨神経刺激法(セイクラル・ニューロモデュレーション)のメカニズムの完璧な理解は多面的であるため、わかりにくい(まだ、アイマイである)」
※「仙骨神経調節はC線維の活動をブロックし、不規則な排尿反応を抑制すると考えられています。」
※「中枢メカニズムの可能性も示唆されている。仙骨神経調節療法で治療に成功した難治性過活動膀胱の患者では、仙骨神経調節療法後にブロードマン脳領域9(特に左背外側前頭前野)が著しく活性化することが示された」
↑
「仙骨神経刺激療法(SNM)」のメカニズムは「不明」で、多くの仮説がある状態ですが、これは鍼灸のメカニズムに類似している可能性は高いです。外科手術で、デバイスを埋め込むため、小児では皮膚に電極を貼る「パラセイクラル・トランスキューテニアス・エレクトリカル・ナーブ・スティミュレーション(PTENS)」も使われています。
いずれも、メカニズムは不明ですが、臨床効果が出ていることが面白いです。